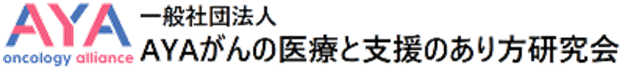一般社団法人AYAがんの医療と支援のあり方研究会
会員 各位
AYA研ニュースでもご案内いたしましたが
来週の金曜日(6月28日)に
いよいよ第1回AYA研ゼミが開講されます。
■■■ 第1回AYA研ゼミ開催! ■■■
第1回AYA研ゼミのテーマは「AYA世代の外見変化を支援する」
AYAの患者さんの外見変化を支援するために必要な視点や
AYAの患者さんに本当に必要な外見の支援は何か?について
みなさんと一緒に考えたいと思います。
日 程:2024年6月28日 [金] 17:30-18:30
会 場:WEB開催[ZOOM ウェビナー]
講 師:藤間 勝子 さん
国立がん研究センター中央病院
アピアランス支援センター センター長
会 費:1,000円(AYA研準会員は有料、正会員/学生会員/賛助会員/団体会員は無料)
定 員:200名
事前申込期間:2024年5月1日~6月22日
https://aya-ken.jp/event/web_zemi1
参加登録をお待ちしております!
■■■【ご案内】アヤスク!オープンスクール(体験会)のお知らせ■■■
キャンサー・ソリューションズ株式会社より
「アヤスク!ピアサポート体験会」の案内依頼があり
AYA研も協力団体として会員の皆さまへご案内をさせて頂きます。
アヤスク!(正式名称:メタバースAYAスクール)は
AYA世代でがんを経験した仲間達との交流や情報収集を目的に開かれたメタバース上の架空の学校です。
AYA世代でがんを体験した方・ご家族が集い、思いを共有し、安心して話せる場所を目指しています。
以下の日程でオープンスクール(体験会)を開催します。
(※参加できる人は、15~39歳(AYA世代)でがんを体験した18歳以上の方とそのご家族です)
アヤスク!に遊びに来てメタバース上の架空の学校を体験してみませんか?
ぜひ、ご興味のありそうな対象者様へご案内をお願いします。
【日時】2024年7月18日(木)14時~15時
【お申込み】https://ws.formzu.net/dist/S28492379/
【申込み締切り】7月11日(木)
<参加対象者>
原則、15~39歳(AYA世代)でがんを体験した18歳以上の方とそのご家族です。
ただし、患者さんへのご案内を検討してのご参加であれば、
医療者、患者会の方なども体験会へご参加いただけます。
●アヤスク!でできること(予定)
①がんになったあとの暮らしを考えるミニ講座
アピアランスケア、栄養と食事、運動など、がん専門医から学べます。
②AYAのリアルを語り合う交流ひろば
就職、学校、心理学・コミュニケーション講座、お金のはなしなど、専門家がサポートします。
③クリスマス会などのパーティやクラブ活動や文化祭などの開催
季節に合わせたイベント、共通の趣味・興味を持つ仲間との部活動などを応援します。
ご不明点はこちらからご連絡ください。
https://ws.formzu.net/dist/S85049932/
たくさんのご参加をお待ちしています。
尚、本体験会は環境省放射線健康管理・健康不安対策事業(放射線の健康影響に係る研究調査事業)「放射線による健康影響不安を考慮したAYA世代がん患者に対する包括的なピアサポート体制の構築研究班(佐治班)」を受けて実施するものです。