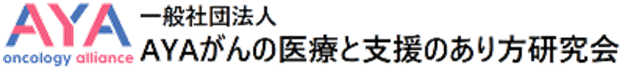2024年12月、オーストラリア・メルボルンで開催された 6th Global AYA Cancer Congress に、AYA研の国際学会参加助成金を頂き、参加することができました。

私は小児がんサバイバーとして、世界のサバイバーと交流を深め、彼らが病気やその後の人生をどう捉え、それをどう役立てているのかを学びたいと思い、この助成に応募しました。そして、特にがん治療後の不妊症について、互いの経験を共有し、各国の医療体制を学ぶことで、自分自身の今後の活動に活かしたいという思いがありました。
Congress初日に行われた、AYAがんサバイバーが参加するワークショップでは、「アドボカシー」をテーマに討論しましたが、海外のサバイバーがサバイバーシップを非常に明確に捉え、自身の経験を積極的に発信している姿がありました。
彼らにとって「語ること」は単なる自己表現ではなく、それが同じ困難を抱える仲間の支えになると同時に、「語ること」そのものがセルフアドボカシーの一環となっていることを実感しました。
そして、4日間を通して彼らはワークショップのファシリテーターやセッションの座長を担い、啓発ムービーを作成するなどして、自身が会議の運営に携わることで、ピアサポート/セルフアドボカシーのモチベーションをさらに高めているように思えました。


そして、閉会の辞で述べられた「この学会は、がんサバイバーが生きていることのセレモニーでもあるんだ」という言葉が深く心に残りました。その瞬間に会場から大きな拍手が沸き起こり、サバイバーからの発信に会場に居合わせた医療者は心を震わせ、「AYAがん患者/サバイバーの良い未来を創っていこう」という雰囲気で一丸となった様子を感じました。日本でも同様の機会が増えると良いと心から思いました。
不妊症に関する各国の医療体制について、特に妊孕性温存療法の提供体制においては、米国では「がん生殖ナビゲーター」という職種が患者やがん治療医(主治医)と生殖医療機関とを繋ぎ、迅速な対応を可能にしている点、オーストラリアではがん治療施設と近隣の生殖医療クリニックとのスムーズな連携が大きな役割を果たしている点が印象的でした。
そして、交流したサバイバーの多くは自身の不妊リスクの程度を明確に把握しており、そのリスクを含めて人生計画を考えているようでした。
一方で、どの国においても不妊症リスクの告知が十分ではない現状が課題として共有されていました。告知を受けずに妊孕性温存術を受けられなかったサバイバーの苦悩の声から、情報や医療の質の均てん化等のさらなる改善が必要であると痛感しました。

また、現地の会場では日本から参加した方々とも交流を持つことが出来ました。夜には食事を囲みながら皆さんのこれまでの活動や経験を共有して頂きましたが、異なる分野や立場で活躍する方々のお話しに大変刺激を受けました。こうした新たなネットワークが広がったことも今回参加して本当に良かったと感じることの一つです。
この度はAYA研の国際学会参加助成を頂き、大変貴重な経験をさせて頂きました。この場を借りて深謝申し上げます。誠にありがとうございました。
今回Global AYA Cancer Congressに参加させて頂き、私はただ学ぶだけでなく、「私自身が声をあげ、行動する側にならなければならない」と強く思いました。まずは、自分の経験をもっと発信すること。AYAがん患者/サバイバー同士が交流できる場をもっと増やすこと。
そして、AYAがん患者/サバイバーが生きていくためのより良いフォローアップ体制を作る活動にも関わっていきたいと考えています。
信州大学医学部小児医学教室
盛田 大介