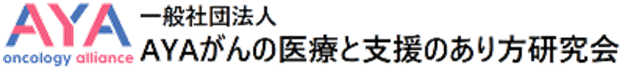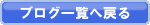吉村 泰典 慶應義塾大学 名誉教授/内閣官房参与の基調講演(右端に鈴木 直さん) |
2020年2月15日、16日と埼玉県大宮市で、埼玉医科大学総合医療センター産婦人科教授の高井 泰さんの主催で、第10回日本がん・生殖医療学会(JSFP)学術集会が開催されました。第1日目の開会式前の「がん・生殖医療と福祉の協働」をテーマとした、市民公開講座では、AYA研理事でJSFP理事長の鈴木 直さんの基調講演から始まり、妊孕性温存のみならず養子・里親制度の話題まで、AYA世代のがん経験者の妊娠・出産、育児など幅広い話題を一般の方々に分かりやすく解説されました。
開会式後の学術集会の初日には、地域連携体制の全国展開、情報提供・意思決定支援体制の質的構築、ネットワークの持続可能性の追求を目指したOncofertility Consortium Japan Meetingが開催されました。そこでは、地域ネットワークの新規構築を目指して活動中の愛知県の現状や課題、遺伝カウンセリングや看護さらに薬剤など多職種の連携の有効性について、実例を用いた報告がされ、最後にJSFP鈴木理事長からの総評で締めくくられました。次の心理支援体制のシンポジウムでも、実際の患者さんの意思決定支援に携わる医師や心理師の立場から、効果的な医療情報の伝え方、教育プログラム、チェックリストを用いたアセスメント、更に困難症例における実際の関わり方など、様々な角度から、現場ですぐに役立つ内容が盛りだくさんでした。
 ワークショップ「がん・生殖医療の量的・質的均てん化と公的助成・登録制度」の風景 |
第2日目午前の「がん・生殖医療の量的・質的均てん化と公的助成・登録制度」と称したワークショップでは、妊孕性温存に関する公的助成金制度の話題、妊孕性温存における安全性や効果に対するエビデンス作りや長期保管における管理上の問題克服などを目的とした全国症例登録制度(JOFR)などの議論から体制整備が議論されました。
 AYA研共催セッション「AYAがん患者の支援とは」では、清水 千佳子さんがAYA支援チームとネットワークの現状について話しました |
学会、最後のAYA研との共催セッションでは、上智大学看護学部の渡邊 知映さん(AYA研理事)、若年性乳がんサポートコミュニティーPink Ringの御舩 美絵さんが座長を務め、国立国際医療研究センター病院の清水 千佳子さん(AYA研副理事長)、国立成育医療センターこころの診療部 田中 恭子さん、大崎市民病院精神科臨床心理士の渡邊 裕美さんが、それぞれAYAがん支援チームとネットワークの現状、A世代の意思決定支援、YA世代の心理的特性を踏まえた支援などについての実践的な講演が好評でした。
その他、最先端の基礎研究の紹介や多くのサバイバーの方々の参加など、盛りだくさんで有意義な二日間でした。会を盛り上げたAYA研会員の皆様、主催者の埼玉医科大学関係者の皆様、本当にお疲れ様でした!
担当:AYA研 広報委員 古井 辰郎
(岐阜大学大学院医学系研究科
産科婦人科学分野)